私は自分の最後を考えたとき、やはり子どもたちのことが一番気になります。子どもたちに幸せになってほしい。子どもたちに感謝を伝えたい…
親としてできることは全うしてから旅立ちたいと思っています。
皆さんは、皆さんの最期のときをどのように生き、どのように締めくくりたいと思いますか?家族や大切な方に何を伝えたいですか?
両親の死や、20年以上看護師として多くの方の最後のときに関わらせていただき感じること。それは元気なうちに、自分の意思をわかるようにしておくことの大切さです。終末期になり言葉を発することができなかったり、認知症になり意思を伝えることができなくなってからでは、自分の本当の思いを伝えることは困難になります。

自分の死後も家族には仲良くしていてほしい。遺産のことなんかで争ってほしくない。お世話になった人たちに感謝を伝えたい。困っている人たちの支援のため寄付したい。そんな願いを叶えることができるのが遺言書です。
人生最後の気持ちを家族や大切な方へ伝えるため、遺言書を作成してみませんか?
遺言書とは?遺言書の種類について
遺言書とは、被相続人が自分の死後に財産をどのように分けるかの意思を示した書面です。これにより故人の希望に沿った遺産分割が可能となり、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
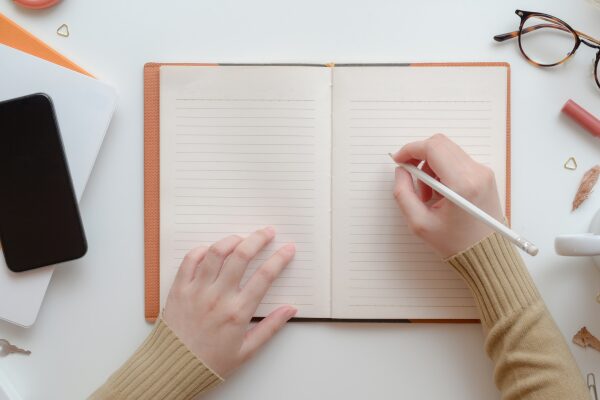
遺言書を作成しておくことで、法定相続人(民法に基づき被相続人の財産を相続する権利を持つ人)以外の人にも財産を譲ることや、相続の分割方法を自由に指定できるメリットがあります。
※国税庁ホームページ【定める相続人の範囲と法定相続分】はこちら
遺言書には主に3つの法的に有効な種類があります。
自筆証書遺言
・自分で全文、日付、氏名を手書きし押印することで作成。
・費用がかからず手軽ですが、不備があると無効になる可能性や紛失のリスクがある。
・家庭裁判所の検認(遺言書が偽造・変造されるのを防ぐために、その存在や内容を確認する手続き)が必要。
※裁判所ホームページ【遺言書の検認】はこちら
・法務局で保管できる自筆証書遺言保管制度がある(2020年施行)。
※法務局ホームページ【自筆証書遺言書保管制度のご案内】はこちら
公正証書遺言
・公証役場(法務局が管轄する施設)で公証人(法務大臣から任命された法律の専門家)が作成し、証人2人の立ち会いが必要。
・原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクがない。
・費用がかかる(費用は相続財産額に応じて異なる)。
※日本公証人連合会【公正証書遺言の作成手数料】はこちら
秘密証書遺言
・遺言内容を記した文書に遺言者(遺言書を作成して自身の財産や意思を死後に実現させようとする人)が署名押印し、封筒に文書を入れ封印。公証人と証人2人以上の前で手続きを行う。
・内容が秘密にできる一方で、検認手続が必要となる。
・費用がかかる(11,000円の手数料と証人一人当たり5,000円~1万円程度)
終活における遺言書の大切さ
終活において遺言書を作成することは、残される家族や大切な人にとっても非常に重要です。
1. 相続トラブルの防止
遺言書を作成することで、相続人間の争いを未然に防ぎ、スムーズな遺産分割が可能になります。
相続では「介護を頑張ったのだから取り分を増やしてほしい!」「同居していたのだから多くもらうのが当然だ!」などと相続人同士でのトラブルが発生することがあります。遺言がないと法定相続分に従って相続されますが、遺産分割協議で揉めることも考えられるのです。
※国税庁ホームページ【定める相続人の範囲と法定相続分】はこちら

明確な遺言があれば、争いを防ぎ、円滑に相続手続きを進めることができます。自分の意思や理由を記載することで、相続人が納得しやすくなります。
2. 生前の意思を反映することができる
誰にどの財産を渡すか具体的に指定でき、相続人意外(例:内縁の配偶者やお世話になった方)にも財産を残すことができます。
例えば、長男の妻は献身的に介護してくれたから、長男の妻にも財産をあげたい。」と願っても、長男の妻は法定相続人ではないため、何もしないと願いを叶えることはできません。しかし遺言書を作成することで長男の妻に感謝の気持ちとして財産を残すことも可能になります。

また法定相続では対応できない「特定の人に多く残したい。」「寄付をしたい。」などの希望を叶えることもできます。
例えば、子どもたちは経済的に自立していて心配ないから配偶者にすべて残したい、児童養護施設に寄付したいなど…自分の思いを叶えることができるのです。
意思が反映されないことも?遺留分侵害請求について
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分侵害請求(相続において最低限もらえる分を(遺留分)を守る仕組み)をする可能性はあります。
遺留分とは一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
※裁判所ホームページ【遺留分侵害額の請求調停】はこちら
3. 家族へ安心感を提供できる
故人の意思が明確に伝わることで、家族はその意思を尊重しやすくなります。
残された方があなたに「何もしてあげられなかった…」と後悔しないためにも、意思を伝えておくことはとても大切なことです。意思を示しておくことであなたの意思を尊重することができれば、残された方も「願いを叶えてあげることができた。」と安心できるのではないでしょうか。

4. 手続きの簡略化による家族の負担を減らすことができる
遺産分割協議が不要になるため、相続人が手続きをスムーズに進めることができ、家族の労力が省け、精神的な負担の軽減につながります。
5. これまでの人生の感謝を伝えられる
遺言書には付言事項(遺言者の気持ちや背景を相続人に伝えるための記載部分)として、法的拘束力はないものの家族への感謝や想いを記すことができます。これまでの人生で関わりをもってくれた方々への感謝を形にすることで、残された人が「愛された」「大切に思ってもらえた」と感じることができるのではないでしょうか。また故人の思いや感謝を知り共有することで、家族間の絆を深めることができます。

大切な人の幸せを願う遺言書
大切な人を失ったとき、大きな悲しみの中に取り残されたような気持ちになります。そんな中でも必要な手続きなどは待ってはくれません。そして、悲しみの中で遺産相続という問題に直面し、望んでもいない争いに巻き込まれてしまうとしたら?
私なら、子どもたちがそんな状況になることは望みません。平穏に過ごしてほしい、幸せに暮らしてほしいと願います。そして、子どもたちに感謝を伝えたい…

遺言書は自分自身の意思を最後まで大切にすることであり、残される方の幸せを願うものであると思います。自分の人生も、大切な人の人生も最後まで大切にすることを実現するツール。それが遺言書なのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日も皆さんと皆さんの大切な方が幸せを選んでいけますように。



コメント